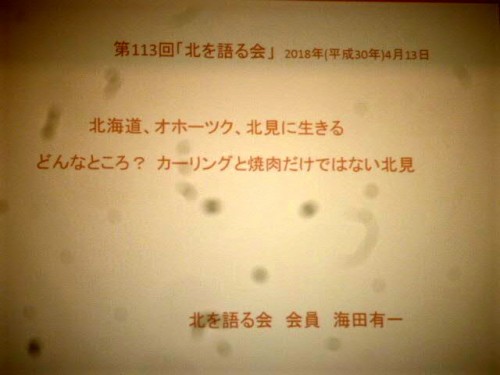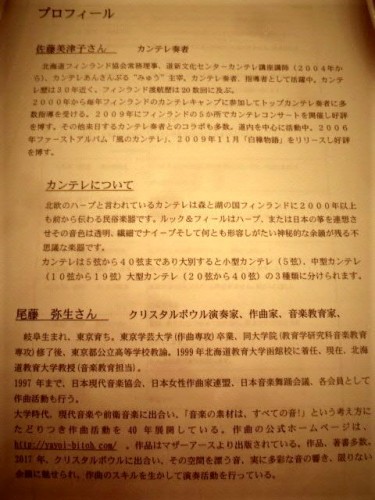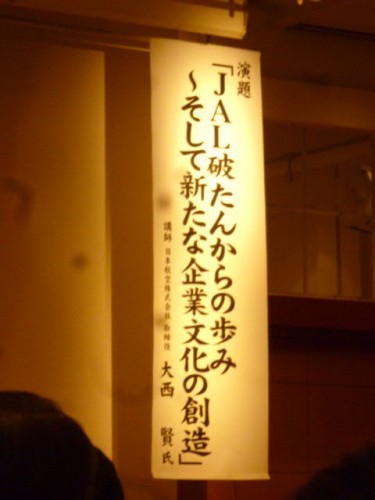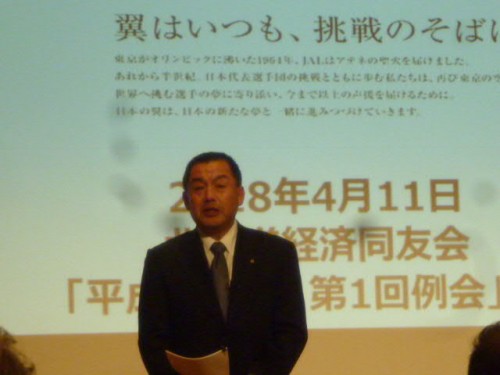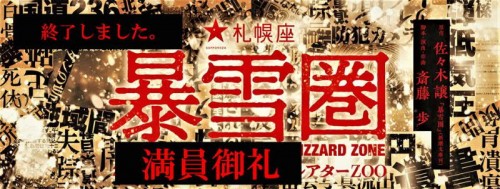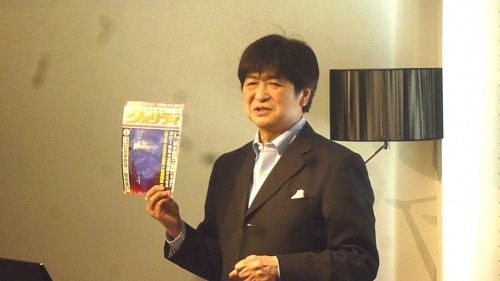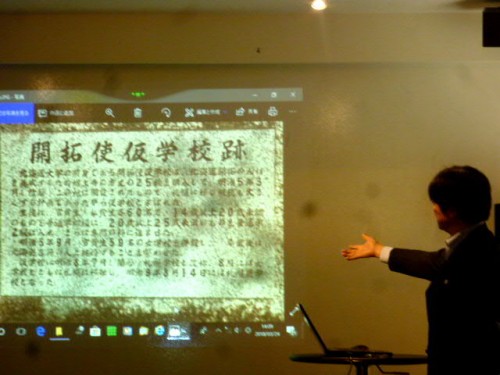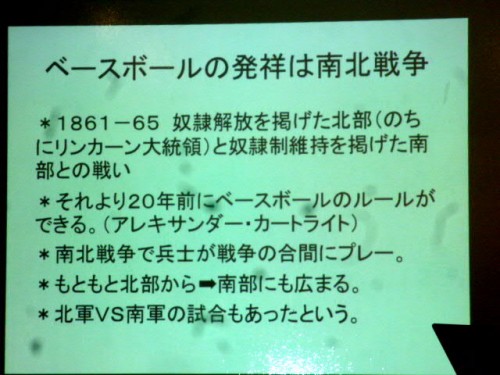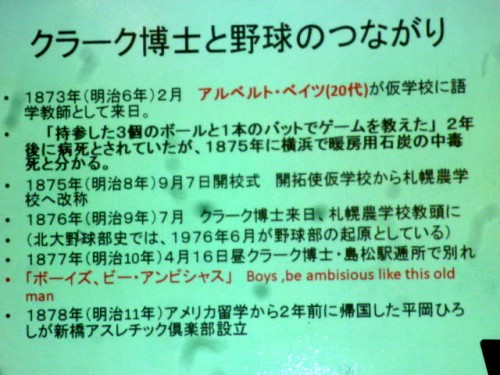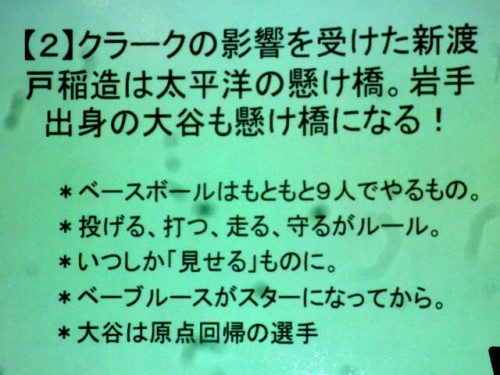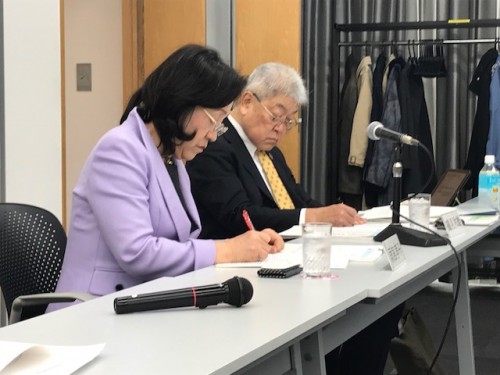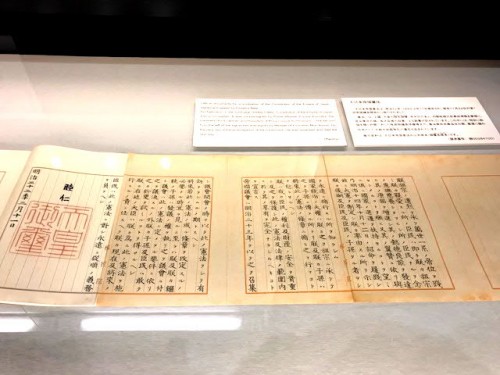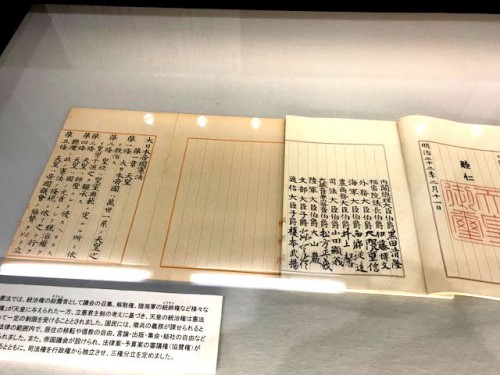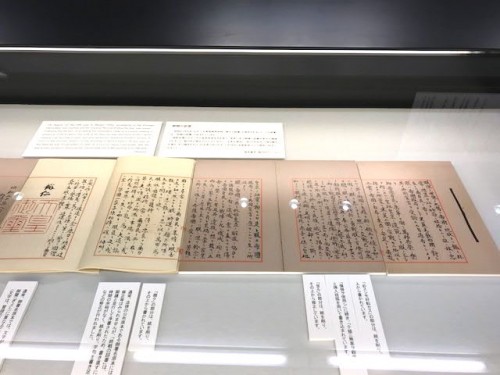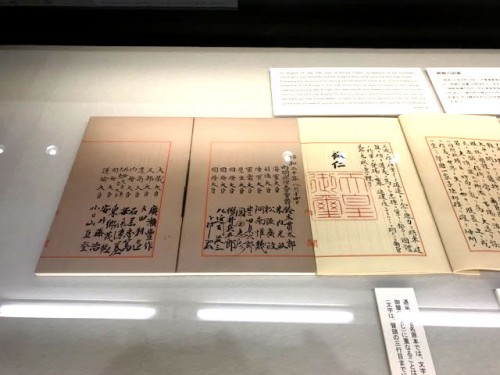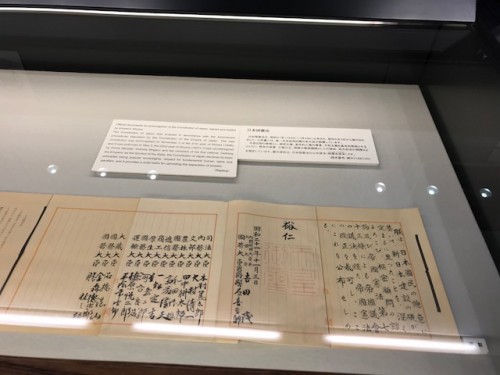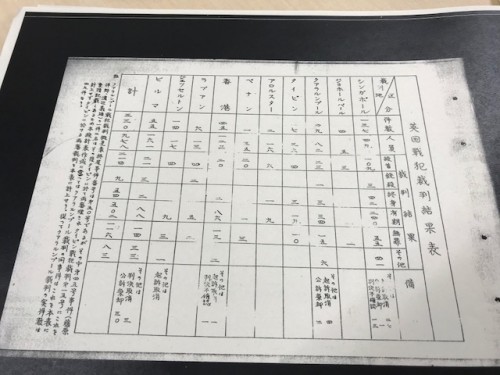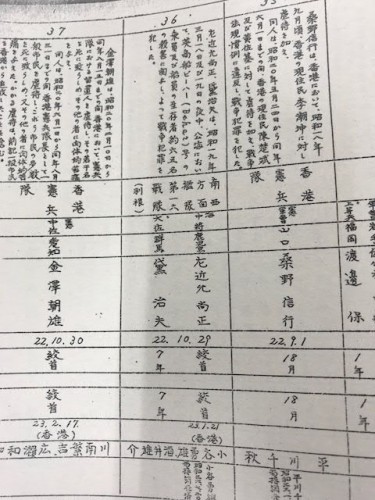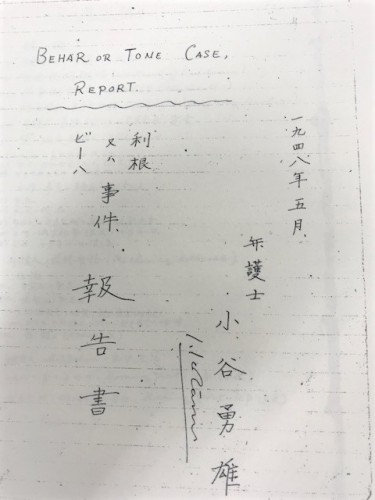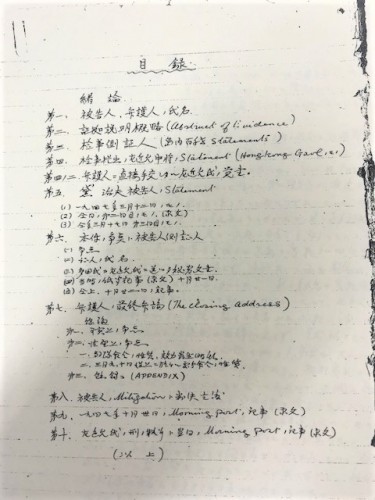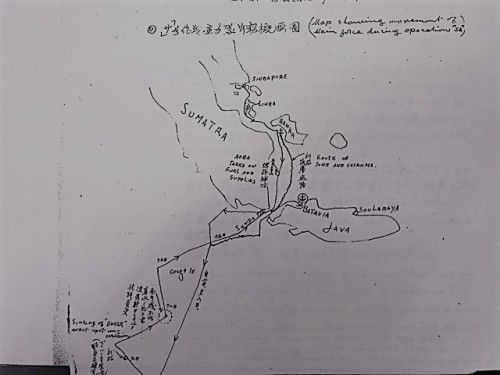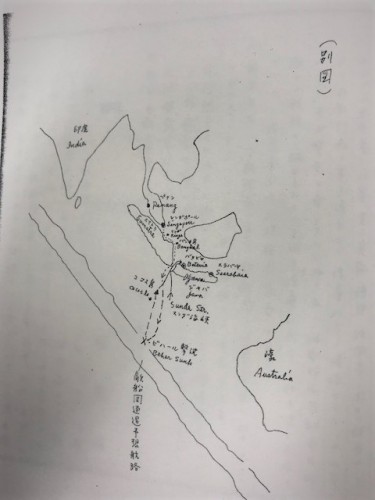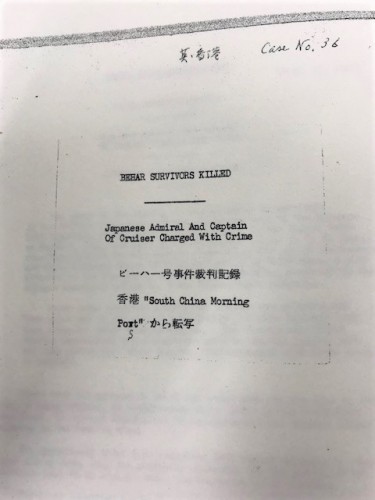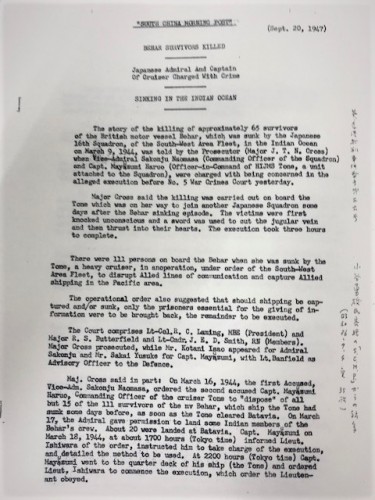2018年4月27日、韓国の文在寅(ムン・ジェイン)大統領と北朝鮮の金正恩(キム・ジョンウン)委員長は、軍事境界線のある板門店で会談し、「板門店宣言」に署名して歴史的な一日となりました。
* 板門店宣言全文:https://article.auone.jp/detail/1/4/8/6_8_r_20180427_1524835601996918
夜のテレビ、NHKニュースに登場していた南山大学教授のコメントは何ともネガティブ。歴史は一挙に変わるはずもなく、まして朝鮮半島の歴史では、基本的には休戦協定の当事者は北朝鮮とアメリカ(国連軍)ですから、構図的には6月にも想定されている米朝会談で正式な新しい枠組み交渉がなされるのは自明の理です。ただ、その前に、南北会議がこのように設定されて共通の目標を掲げたその両者の勇気に、率直にまずは拍手なのではありませんか。私は、1989年のロシア崩壊、ベルリンの壁の撤去の瞬間を思い出しました、まさに20世紀の冷戦構造の終結です。7年前にベルリンを訪問した時、その瞬間を自らの肌で感じました。
* http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=10458
今回、金正恩氏は北朝鮮の指導者として初めて軍事境界線を200mの徒歩で越え、韓国側に足を踏み入れました。午前は韓国側施設「平和の家」で同席者を交えて1時間40分会談、午後にも屋外を散策する途中で約40分間2人だけで会談し、その後で共同記者発表に臨みました。私はテレビでその様子を見ていて、共通の言語・民族が、もちろん世界の目を意識してではありますが、向き合って話す姿に、まさに歴史の瞬間に立ち会っている気がしました。
宣言では「完全非核化」のほかに、朝鮮半島の平和構築に関しては「非正常的な現在の停戦状態を終息させ、確固たる平和体制を樹立することは歴史的課題」と指摘し、年内に朝鮮戦争の終戦を宣言したうえで、1953年に締結した休戦協定を平和協定に転換するため、南北米の3者或いは中国を加えた4者による会談を進めると明記しました。
南北の緊張緩和のため、互いに武力を使用せず1992年の南北基本合意書で約束した「不可侵」の合意を再確認し順守するとし、来る5月1日から、南北の軍事境界線付近で拡声器を使って流してきた北朝鮮の住民向けの宣伝放送を中止し「すべての敵対行為を中止する」と宣言しました。
南北は相互交流の拡大のため、北朝鮮の開城に南北共同連絡事務所を設ける方針も確認。経済協力に関しては、2007年の南北首脳会談で触れた事項を積極的に進め、鉄道や道路などの整備に関して対策を講じるとも明記しています。
私は10年前に、演劇交流で韓国を訪問した時に、板門店ツアーに参加して現地に足を運びました。歴史の最前線にいる緊張感は今も心に残っています。
* 板門店 http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=876
その時の私のコメントです~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
いずれにせよ、相変わらずの日本外交の貧弱さを痛感しています、公式発表はともかく、複数の人的パイプがないというか。外交上は、今こそ、東アジアにおける平和と安全に関して「非核化」をキーワードにして、日本は本来のリーダーシップを発揮する時だと思います。そして、一味違う視点として、自然科学者・環境科学者を中心として、たとえば「オホーツク海の生態系」、「北東アジアの大気汚染」、「朝鮮半島の生態系」といったテーマでの、周辺6・7カ国ネットワーク形成プロジェクトを、日本がリーダーシップを取って場の構築等は出来ないものでしょうか。
過去の歴史を受け止めながら、21世紀的テーマの新しい構想の中で平和の時代を創る、そんな時代なのだと強く思います。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~引用 おわり
あれから10年を経て、何も動いていなかった日本国の姿勢、歴史の舞台から取り残される所以ですね。第二次世界大戦の戦勝国がどこで、敗戦国がどこだったのか、あらためて近い歴史をしっかり認識する必要があります、以前から私自身、声高に言ってきたことではありますが。日本は、アメリカに敗けただけでなく中国にも敗けた事実を認識しなければならず、そして、戦前、朝鮮半島を統治していたのは日本であり、中国の一部を占領していたのも日本であることを、ですね。今回の朝鮮半島の平和的統一への努力を、ただ「歓迎」といっている場合ではなく、何がしかの歴史的責任を負っての使命があるのでは、と私は強く思います。
10年前の板門店ツアーで、向かうバスの中で聴いた「イムジン河」は、ひと際印象的でした。1969年前後の私の学生時代とも重なります。
* イムジン河 https://www.youtube.com/watch?v=eQF1xdghzGM
東西ドイツの統合のように、今後、課題は多いでしょうが、南北朝鮮の統合により朝鮮半島の非核化への道が開かれると、韓国駐留のアメリカ軍の位置づけが変わり、ひいては日本の沖縄を中心にいるアメリカ軍基地にも変化が出てくることになります。まさに、朝鮮半島問題は、21世紀の日本のあるべき姿の課題に直結します。
平和への道筋、一歩一歩前に進んでほしいものです、朝から興奮した2018年4月27日でした。