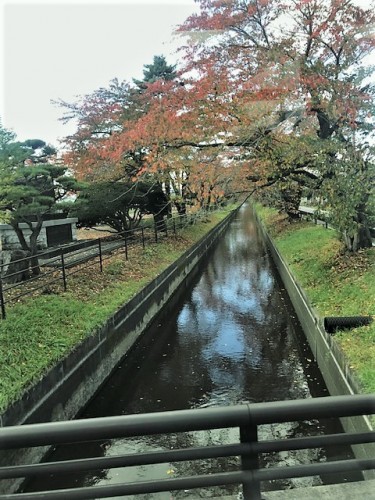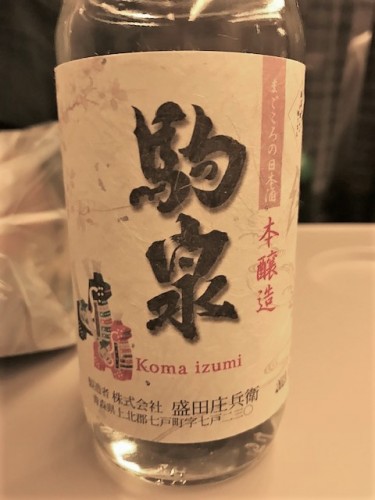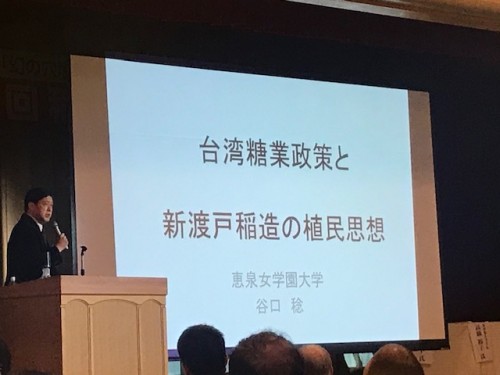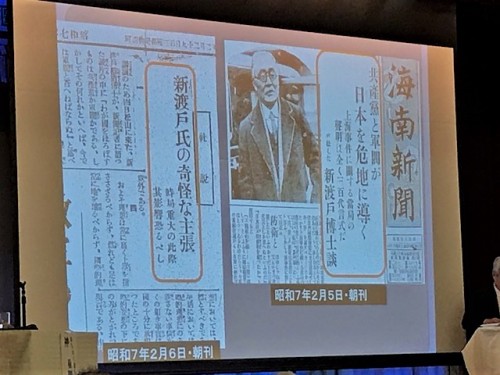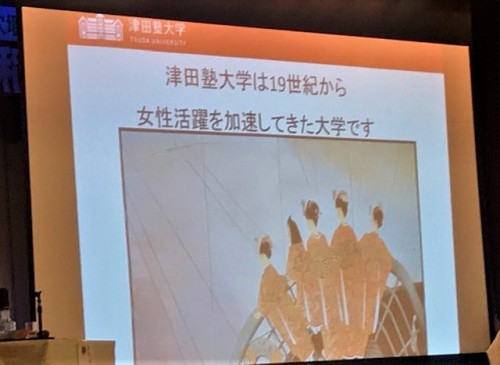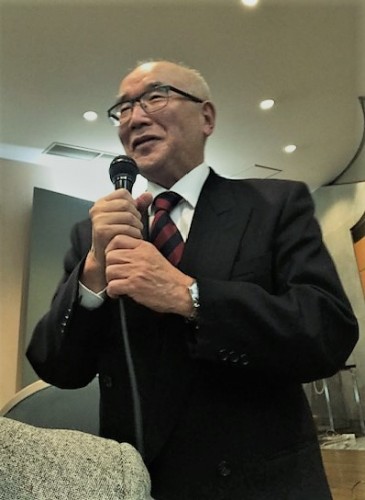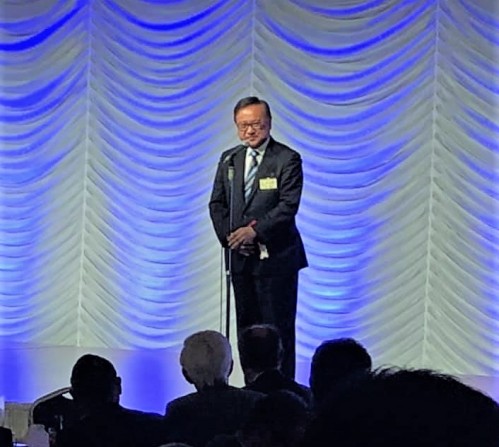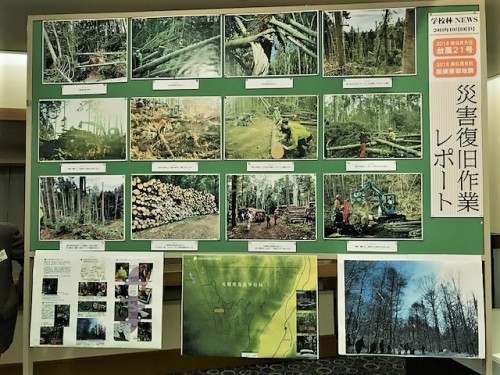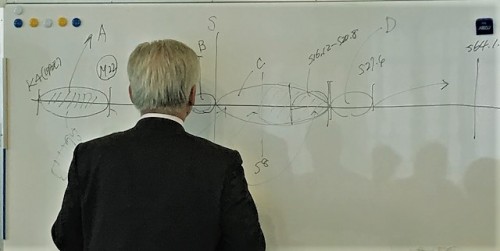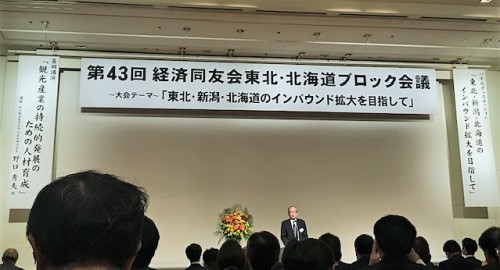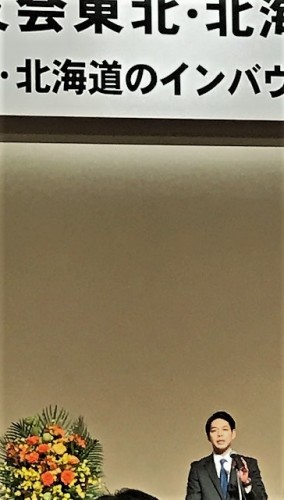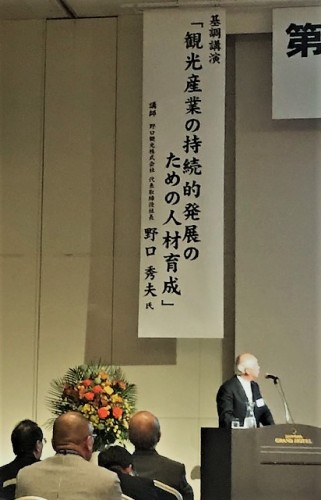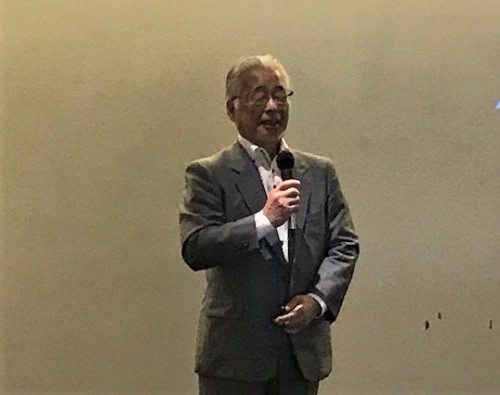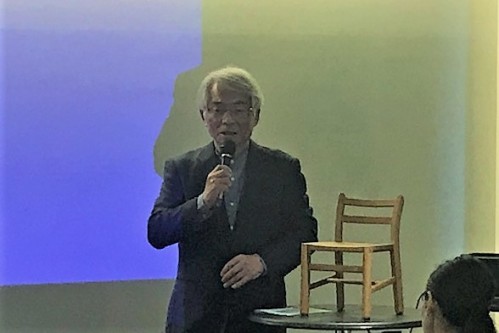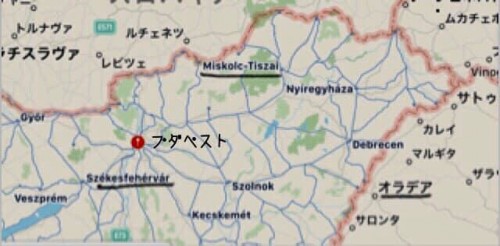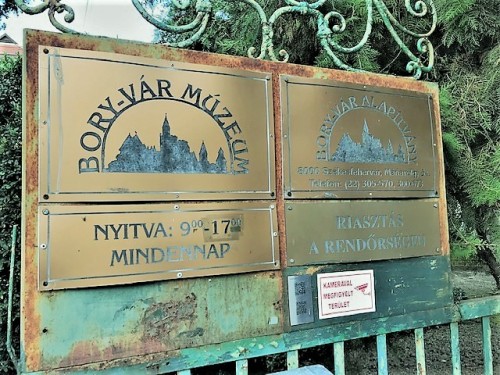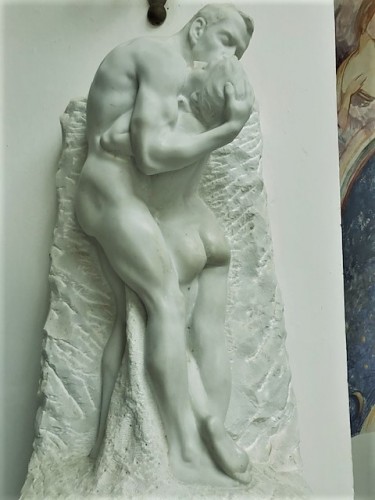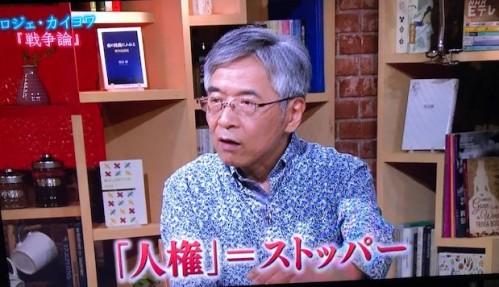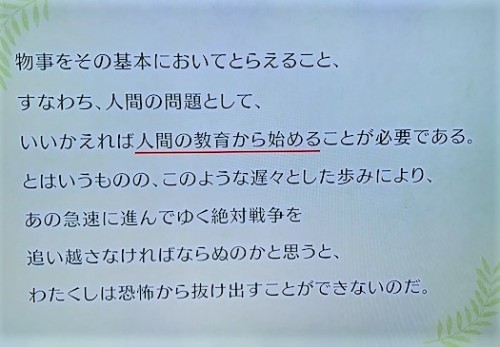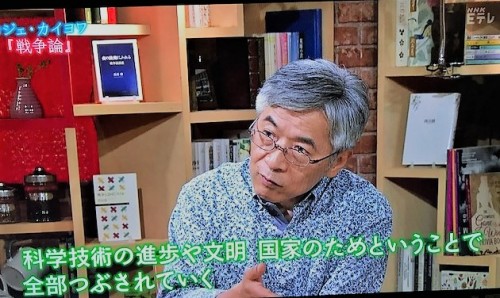スウェーデンの16歳のグレタ・トゥーンベリさんは、先月23日、ニューヨークで開かれた国連気候行動サミットに出席し、地球温暖化に本気で取り組んでいない大人たちに対して怒りの演説を行いました。温暖化解決のための具体的な行動を取らないのであれば、「結果とともに生きなければいけない若い世代」はあなたたちを許さないと、「How dare you !」と何回も訴えました。「あなたたち」は、まさに「私」に向けられたメッセージ、強く胸に刺さってきます。
* https://www.huffingtonpost.jp/entry/greta-thunberg-un-speech_jp_5d8959e6e4b0938b5932fcb6

グレタ・トゥーンベリさん
グレタさんの演説から抜粋~~~~~~~~~~~~~
私から皆さんへのメッセージ、それは「私たちはあなたたちを見ている」、ということです。あなたたちが話しているのは、お金のことと経済発展がいつまでも続くというおとぎ話ばかり。恥ずかしくないんでしょうか!
あなたたちは、私たちを失望させている。しかし、若い世代はあなたたちの裏切りに気づき始めています。未来の世代の目は、あなたたちに向けられている。もしあなたたちが裏切ることを選ぶのであれば、私たちは決して許しません。
私たちはこのまま、あなたたちを見逃すわけにはいかない。今この場所、この時点で一線を引きます。世界は目覚め始めています。変化が訪れようとしています。あなたたちが望もうが望むまいが。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 引用おわり
私がFacebookにこの記事を投稿したところ、以下のようなレスポンスがありました。
+++++++++++++
A氏*** 怒りを込めたスピーチに感動。あちこちで戦闘なんかしてないで地球の未来のために各国のリーダーは地球温暖化をくい止めるすべを真剣に検討して欲しいです。子供達にも今の現状を伝えねば、、、
B氏*** スエ―デンのグレタ・トウンベリと言う16才の少女が国連で「地球温暖化」の抑制演説で脚光を浴びている。地球温暖化は紛れもない事実!しかしその原因を探ると、まず化石燃料の酷使があげられる。つまりCO2(二酸化炭素)による成層圏汚染の為、異常気象が世界中で勃発している事実です。
グレタはこの二酸化炭素の拡散の要因を列強国の経済発展と富豪のみにその因果関係を追及しているが、実践可能な解決案を提示していない。これも問題だ。ではCO2拡散となる全ての要因を直ちに止めるべきだとなぜ言わないのか !原発と火力発電を止めよ、と言っているが、原発によるCO2拡散はゼロであることを彼女は知らない。
また、異常気象がもたらす被害は想像を絶する事実は認識するが、一方それによって風力発電施設が壊滅され、太陽電力発電施設が壊滅され、ダムが破壊されているのも事実である。しかも化石燃料は枯渇する。再エネとて異常気象の前には虫けら同然となる。したがって異常気象による災害に影響されない発電方法を訴える方がはるかに有意義であると言うものです。その一つに原発がある。少なくとも原発は如何なる異常気象にもビクともしないのが現状である。
私は電力を制する国家が世界をも制すると考えます。猛暑や厳寒にはエアコンで対処できるし、養殖産業、植物工場は食を生産できる、しかしそこに必要なのは膨大な電力であると考えます。
理想を語ることは容易だ。しかし実践可能な現実を考慮した場合、グレタの呼びかけは「片手落ち」と考えます。グレタには一日も早く高校を卒業し、大学でもっと専門的な教養を身に付けて欲しいものです。
ところで最もCO2を拡散するものに航空機がある。スエ―デンからニューヨークまで旅をしてきたグレタの交通手段は何であったのかと考えるのは私だけであろうか。
~~~私の返信: 私がお伝えしたかったのは、彼女がなぜここに立っているのか、ごく普通の中学生でいられない状況に追い詰めてきた我々の世代の責任を痛感する、そういうことです。
<以下記事の引用>
グレタさんは、自身のツイッターで、温室効果ガスの排出を避けるため、飛行機に乗ることを2015年から拒否していると明かしている。そのため、今回の講演がおこなわれたアメリカまで、イギリスからヨットで大西洋横断を行った。
「マリツィアII号」と名付けられたヨットは全長18メートル。風で動くが、デッキと側面にソーラーパネルがあり、2つの水力発電機によって電力が供給されている。ヨットに乗船したのは、グレタさんのほか、父親のスバンテ氏、ドキュメンタリー作家、モナコヨットクラブの副会長、そして世界一周を経験したヘルマン船長の合計5人。自然界に廃棄物を排出しないヨットは、飛行機で8時間ほどの距離を2週間かけてアメリカに到着。グレタさんは、「時間感覚が失われ、日付がわからない」とツイートしていた。
グレタさんは、今後、ニューヨークからカナダのモントリオールに渡り、世界的な抗議日になると予想されるストライキに参加する。その後、メキシコやチリで抗議活動を続ける予定だ。問題なのは、アメリカからヨーロッパに帰る方法が決まってないことだ。グレタさん自身、「どうやって母国に帰っていいのかわからない」と話している。
=====引用おわり
~~私の返信: ここまで16歳の彼女を追い詰めていいのでしょうか?
C氏*** 私も彼女がヨットでニューヨークに行く事を発表聞いて注目していました、国連のあの場所であれだけのスピーチさせてしまった事に戸惑いと後悔の思い持ち複雑です。ナノプラスチック問題含め環境後遺症を如何に社会システム変更させるか作り上げてきた我々の最後の仕事責任の様に感じています。
+++++++++++++
彼女の演説に対しては、ヘイトに近いSNS投稿も多いようですが、私自身には胸にぐさりと突き刺さるメッセージでした。これまでの約70年の人生、戦後日本のいろいろあったけど戦争の無かった時代に教育を受けた私ですが、どうやら時代の中では理想的な社会の一員としては力及ばずだったようです。でも、まだ残りの人生、やれることをやっていかなくてはと覚悟を新たにさせてくれたグレタの訴えでした。