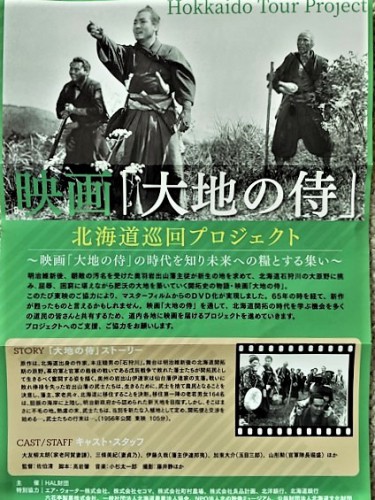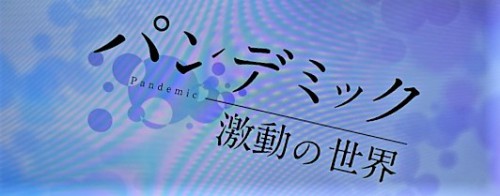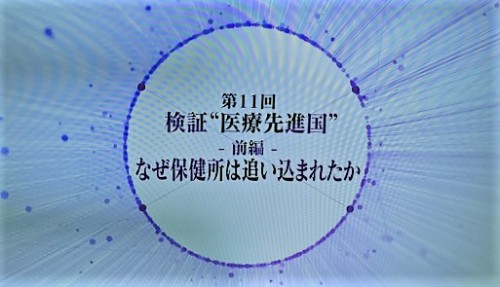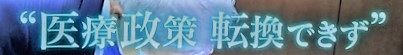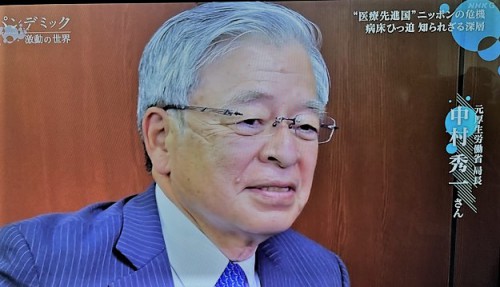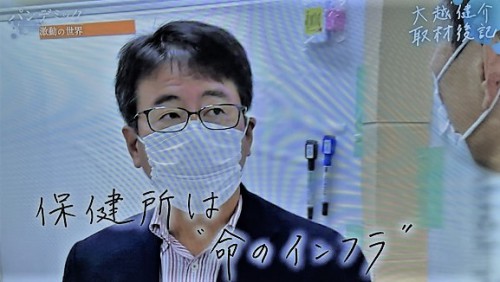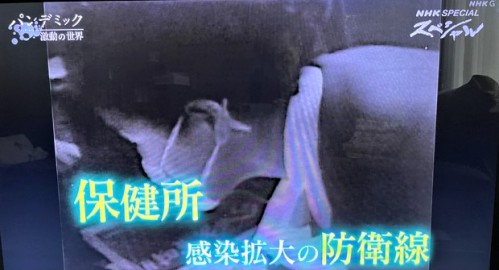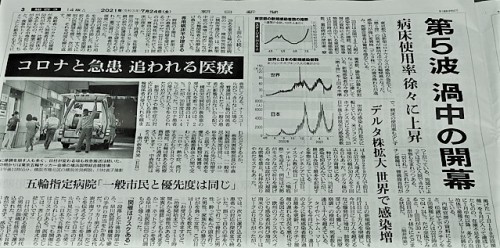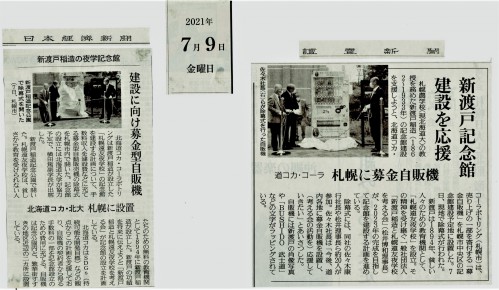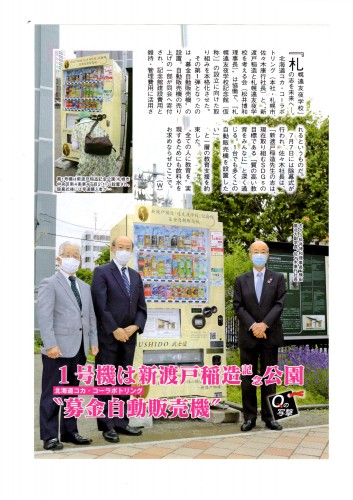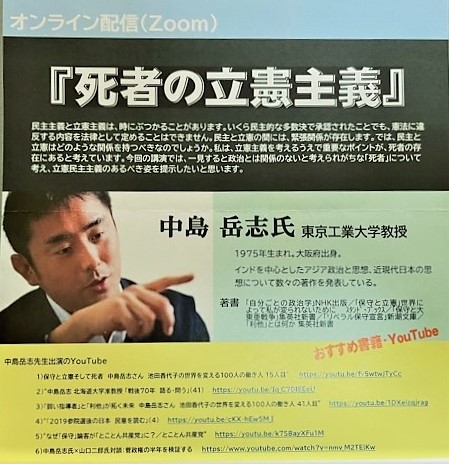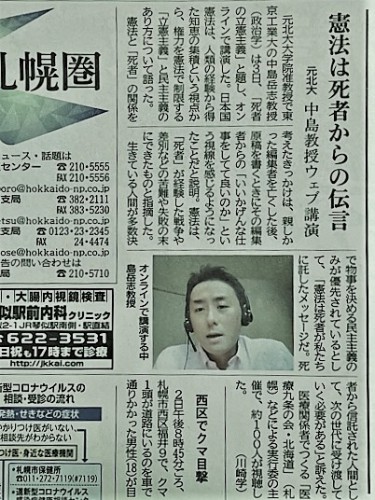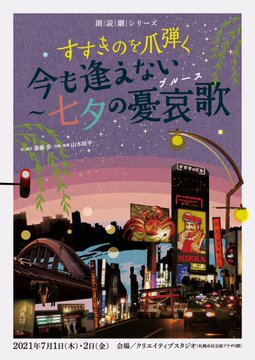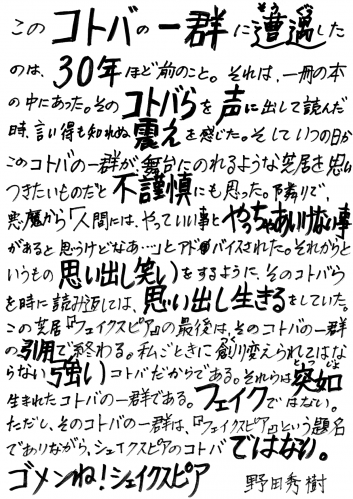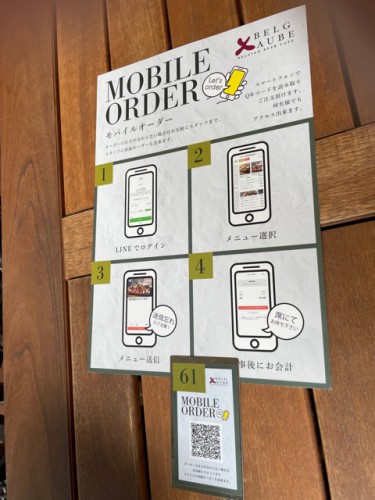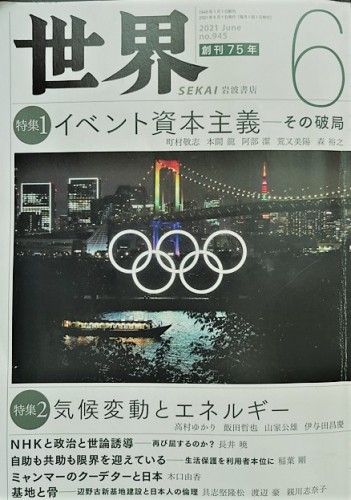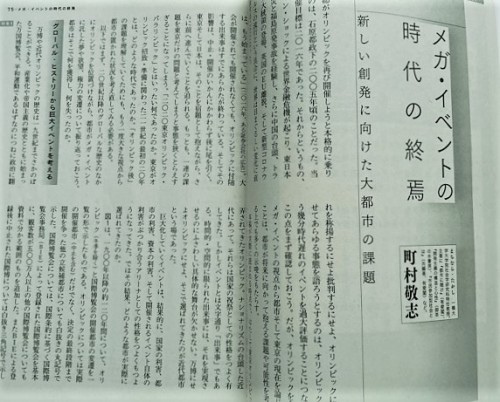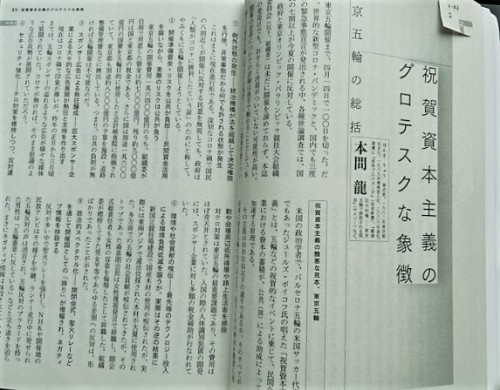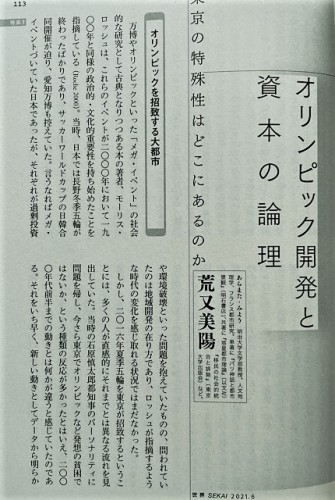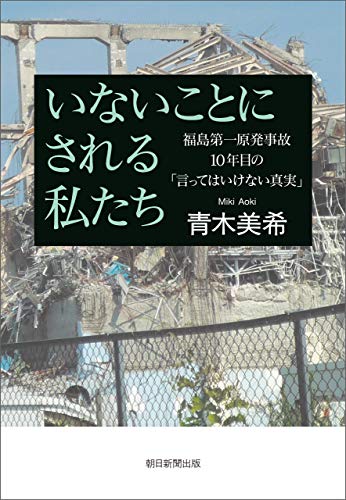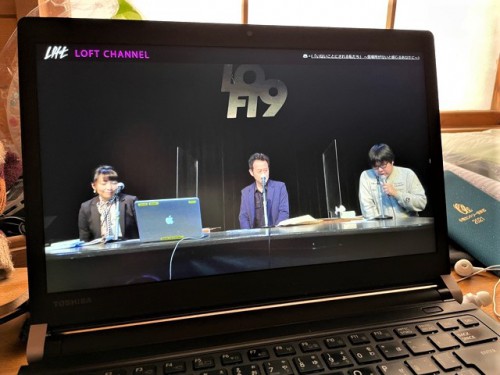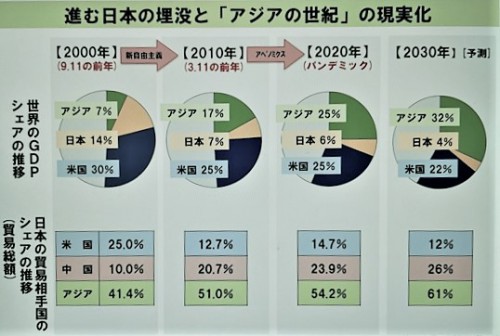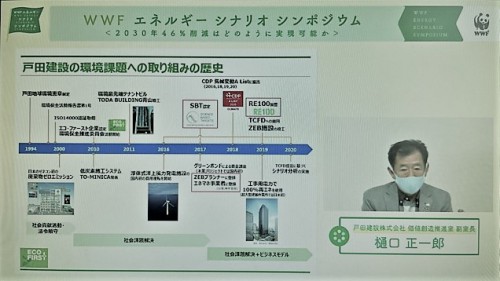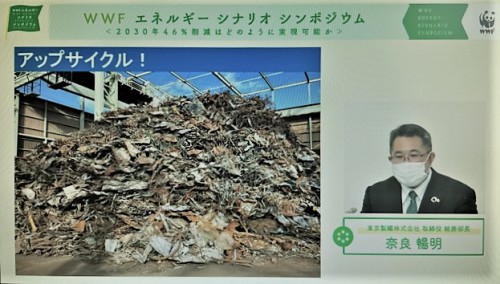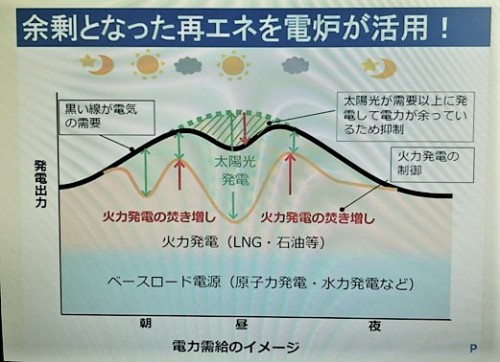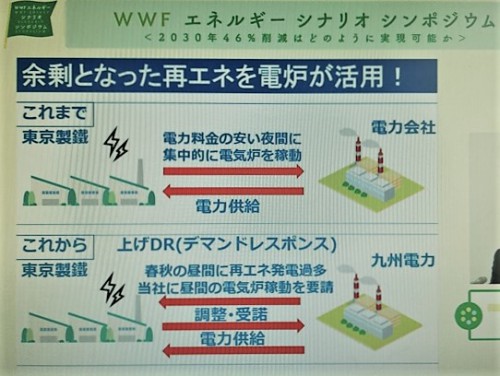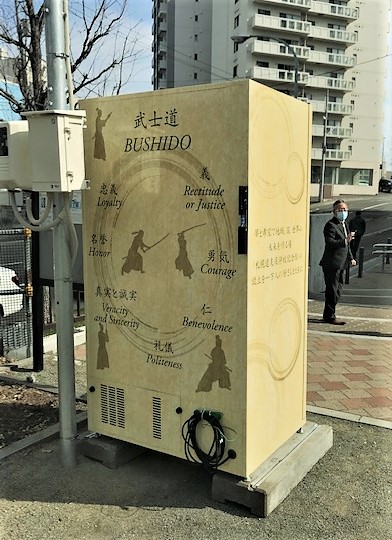映画『ヒノマルソウル~舞台裏の英雄たち(https://hinomaru-soul.jp/)』は、この種の実話を映画化した作品としては際立って優れたものであり、感動しました。特にキャスティングでは、テストジャンパー高橋竜二役の山田裕貴が素晴らしく、彼の眼の美しさが印象的。更にテストジャンプコーチ・神崎幸一役の古田新太も魅力的でした。


以前、私はこれに関する記事を書いています。
http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=32494
そしてさらに、テレビ番組でもこの映画に関しての特集も組まれて、観終わった後もその余韻に浸っています。
https://www.youtube.com/watch?v=8PkVtKGGvGg&t=1482s
この作品のHPより~~~~~
主人公はスキージャンパーの西方仁也(にしかた・じんや)。1994年のリレハンメルオリンピックスキージャンプ団体戦で“日の丸飛行隊”のメンバーとして日本代表を牽引するも、エース原田雅彦のジャンプ失敗で金メダルを逃し、長野オリンピックでの雪辱を誓い日々練習に励み、代表候補として有力視されていながら、惜しくも落選。テストジャンパーとなり日本代表選手たちを裏方として支えた人物です。
物語は、西方の金メダルへの強い想い、それを打ち砕く挫折、原田との友情、怒りと嫉妬、それでも仲間の為に、日本の為に、命の危険を顧みずテストジャンプに挑む、深い人間ドラマを映し出します。また、映画の中では、聴覚障害がありながらも、国際スキージャンプ競技大会で優勝した実在の選手・高橋竜二や、ケガを負ったことでトラウマを抱えた選手、また女子スキージャンプがオリンピック種目になかった当時、テストジャンパーとしてでも長野オリンピックに参加したいという熱い想いを持った実在の選手・葛西賀子をモデルにした、唯一の女子高校生ジャンパーなど、様々な背景を背負ったテストジャンパーたちの熱い想いや、葛藤も色濃く描かれます。
長野オリンピックでの手に汗握る団体戦の攻防、吹雪による競技中断、そんな中、競技が再開できるかを図るために行われた、西方率いる25人のテストジャンパーたちの決死のジャンプを、実話に基づいてダイナミックに描いたオリジナルストーリーです。
原田選手が金メダル獲得後インタビューで語った「俺じゃないよ。みんななんだ。みんな。」という言葉は、岡部・齋藤・船木ら代表選手だけでなく、裏方に徹し日本選手団を支えた親友・西方、そしてテストジャンパーたちにも向けられた言葉だったのです。そんな西方と原田の熱い友情と絆、そして25人のテストジャンパーたちと日本代表選手たち、それを支える家族や関係者たちの想いを知った時、誰もが心を打たれる感涙必至のヒューマンドラマです。
主人公・西方仁也を演じるのは「おっさんずラブ」シリーズ、ドラマ「あなたの番です」など、人気実力を兼ね備えた俳優・田中圭。西方の揺れ動く内面、葛藤を、圧倒的な存在感と演技力で力強く演じ切ります。その他、西方を支える妻・幸枝役に土屋太鳳、テストジャンパー高橋竜二役に山田裕貴、南川崇役に眞栄田郷敦、小林賀子役に小坂菜緒(日向坂46)、日本代表選手・原田雅彦役に『カメラを止めるな!』でお馴染みの濱津隆之、同じく日本代表選手で今なお現役のレジェンド・葛西紀明役に落合モトキ、テストジャンプコーチ・神崎幸一役に古田新太と、若手からベテランまで豪華な俳優陣が大集結! 熱い人間ドラマを大いに盛り上げます。監督には、『荒川アンダー ザ ブリッジ THE MOVIE』で大きな注目を集め、様々な分野で才能を発揮する映像作家・飯塚健。秀逸なテンポ感の中で、しっかりと人間模様を描く演出力に定評があり、涙無くしては観る事の出来ない、感動作品を描き上げます!
さらに、主題歌を、昨年末に放送された第71回NHK紅白歌合戦で大トリを務め、圧巻のパフォーマンスで日本中を感動の渦に巻き込んだMISIAが担当。主題歌「想いはらはらと」はMISIAと初コラボレーションとなる川谷絵音(ゲスの極み乙女。)が作詞作曲。優しくも力強いMISIAの歌声が、金メダルの命運を握ることになったテストジャンパーたち、彼らを支えた家族…すべての舞台裏の英雄たちの背中をそっと押す、応援歌のような本楽曲にもぜひご注目ください。また、挿入歌をMAN WITH A MISSIONが担当。バンド名の意味「使命を持った男」という言葉が本作の主人公西方仁也を物語るような彼らの楽曲「Perfect Clarity」が、西方を始めとしたテストジャンパーたちや日本代表選手の想いを表出するがごとく、映画のクライマックスシーンを大いに盛り上げます。
~~~~~~~~