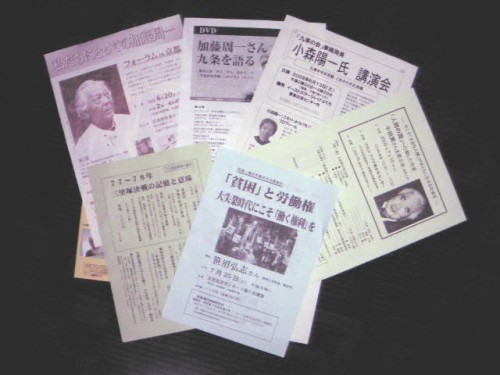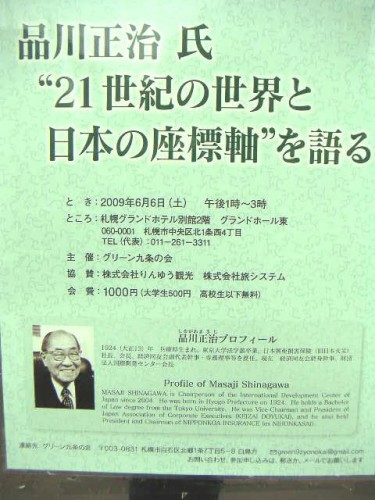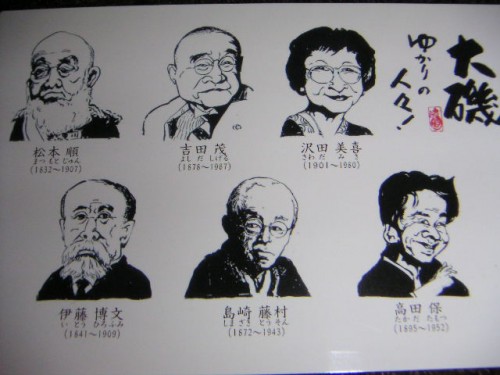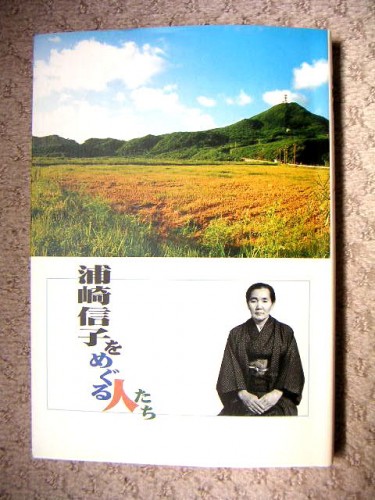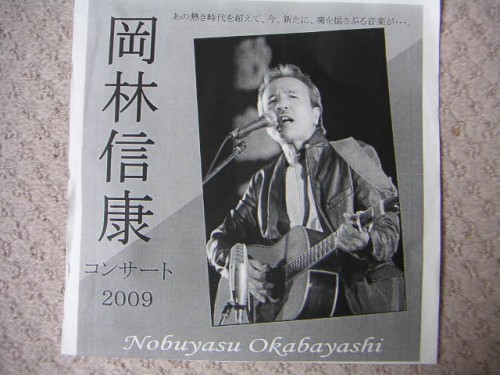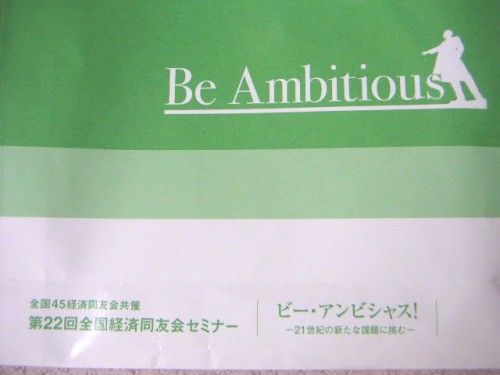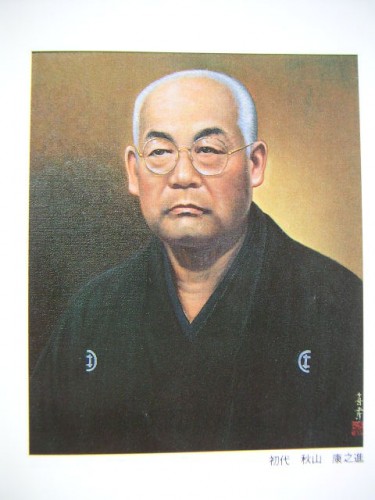毎年4月、「経済同友会http://www.doyukai.or.jp/全国セミナー」が、各地持ち回りで開催されています。今年は17年ぶりに札幌で2日間行われました。北海道は4月よりも5月の方が気候も宜しいということで5月になりました。私は、北海道経済同友会の幹事で、この6年間は毎年参加しています。その時々のテーマを振り返ると、その年の経営課題を推し計る事も出来ます。この数年、登録は1000人を越えていましたが、昨年9月以降の不況とごく最近のインフルエンザの影響で参加者数が心配されていました。しかし888人と予想を上回る登録参加数で、北海道人気の高さをあらためて感じました。2日目の締めのご挨拶で桜井代表幹事は、「20世紀的な規模の拡大を追い求める開催はもうやめにしましょう。21世紀は質の追求の時代で、我々の価値観も変革しなくてはなりません」と語りました。
今年のテーマは、「ビー・アンビシャス!-21世紀の新たな課題に挑む」でした。
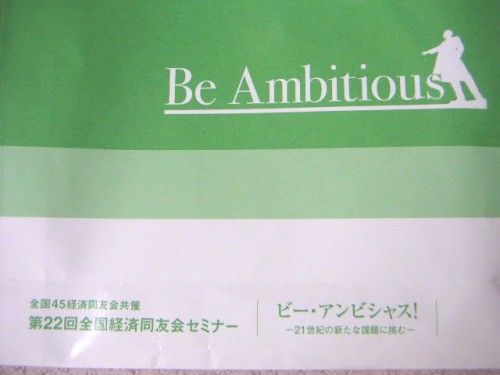
- フォーラム参加者の紙袋
基調講演・分科会・特別講演のテーマは以下です。
基調講演「iPS細胞がつくる新しい医学」 京都大学教授 山中伸弥 氏
分科会1:「低炭素社会実現に向けた取り組みと日本の貢献」
分科会2:「資源問題に直面する日本の針路を考える」
分科会3:「東アジアの交流拡大を考える」
分科会4:「地域資源のブランド化を考える」
特別講演「動物園経営から学ぶもの」 旭山動物園 名誉園長 小菅正夫 氏
今のような時期に、全国から集まった経営者の方々と情報共有が行えたのは、大変有意義でした。
主な経済団体には、経団連(地元では道経連:近藤会長)、日本商工会議所(地元では札幌商工会議所:高向会頭)、それに経済同友会(地元では北海道経済同友会:坂本・吉野代表幹事)がありますが、唯一経営者個人の登録である団体が経済同友会です。上場企業をはじめ企業経営者が個々の頭で考えての提言は、経団連の政治的・業界的立場を踏まえた発言とは一線を画しています。特に地球温暖化等の環境問題へのスタンスではかなり違っていると私は思います。
基調講演の山中先生のお話からは、日本とアメリカの研究環境の大きな違いを知る事が出来ました。
分科会パネラーの中でひときわ印象的だったのは、立命館アジア太平洋大学http://www.apu.ac.jp/home/学長モンテ・カセム氏(スリランカ出身)の発言でした。「教育はビジネスではない、志である」、「人材育成は迷いを希望にかえるものである」、「日本は世界から信頼されているが、友情を抱かれていない」等、ストレートに心に届くメッセージの数々に、会場内は興奮していました。
セミナー終わりの桜井代表幹事のご挨拶は、「今年のスイスで開催されたダボス会議でも、世界の方向性が大きく変わってきている。今までの価値観の限界を、各国・地域・ひとりひとりが認識しはじめている一方で、日本国内の経営者の意識の低さに、強い危機感を持っている。今回のセミナーは、次の新しい価値観は何かを探る議論だった。新しい時代の新しい価値観を求めて、今後も現実と真摯に向き合って努力して参りたい」とのメッセージでした。
ただセミナーを通して気になったのは司会者・パネラーの経営者の発言で、語尾が不明確、口の中でモゴモゴと言葉を飲み込んでしまう方が多かったこと、こういった会社の社員は社長のお話をいつもきっちり聞くことが出来ているのでしょうかね。そう言った事がこれまで指摘もされずに今日に至っている現実が危機的です。経営者はいつでも「裸の王様」になってしまいます。
1日目の懇親会では、ラーメン・カニ等地場産品に大行列で、800食以上用意した品があっという間になくなりました。翌日の朝、本州からいらっしゃった方々の会話をもれ聞くと、「ラーメン横丁に行ってきたよ」、「大通公園のライラックが綺麗でした」、「北大構内も良かったよ」、「ホテルの貸自転車で朝まわってきたけれど、すごく気持が良かった」、「地下鉄も便利で車両も大きいね」・・・・、あらためて札幌のマチを惚れ直しです。
来年のこのセミナーは、四月に土佐で開催されます。常に権力に対して勇気を持って活動していた心意気を、次年度開催地の代表の方が力強く語っていました。ひとくくりで「企業」とは言っても、21世紀の新しい価値観を模索する企業もあれば、相変わらず従来型の延長で経営する企業もあり、経営者の見識で結果も自ずから明確になるでしょう。「理念」が問われているのです。