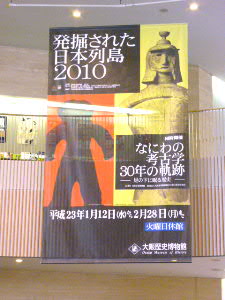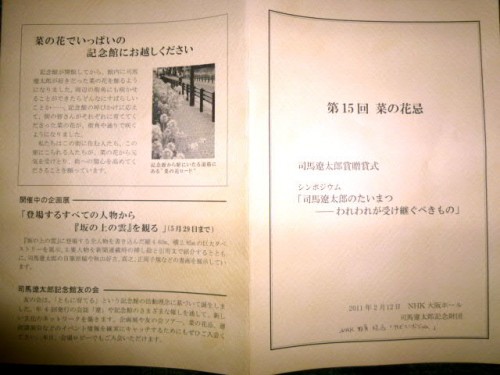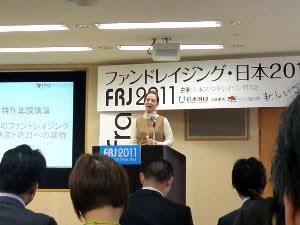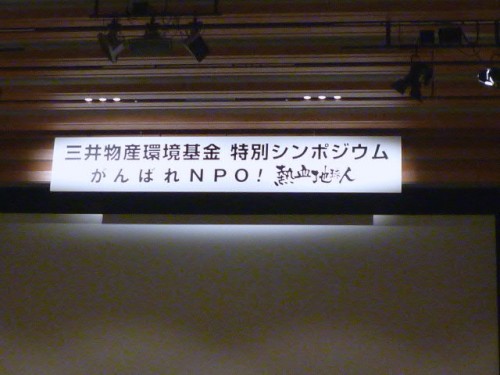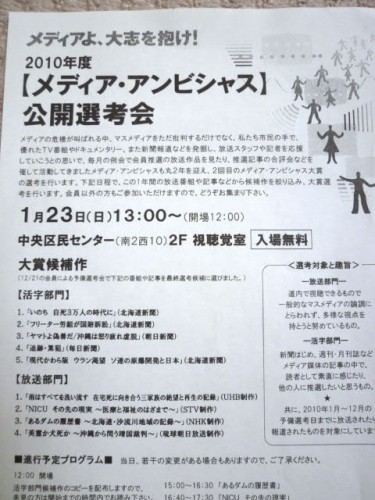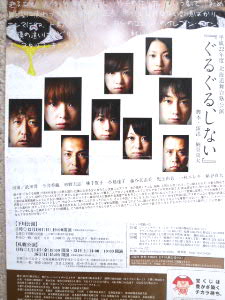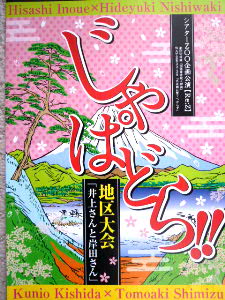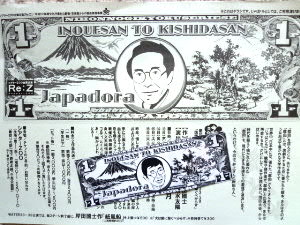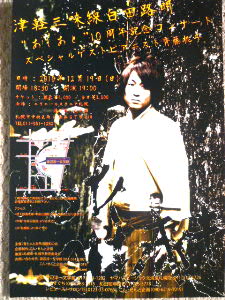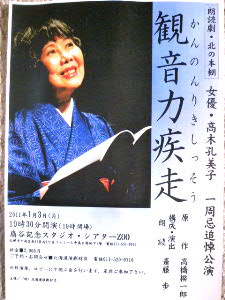公益財団法人助成財団センター(http://www.jfc.or.jp/)主催の「助成財団の集い:http://www.jfc.or.jp/tsudoi2010.pdf」が、180名を越える参加者で、今年も開催されました。
前半は内閣府の方から、一連の「移行認定」に関して、これまでのご報告と今後の留意点等について、ご説明がありました。後半は、下記のメンバーでのシンポジウムで、私もシンポジストの一人として参加する機会を得ました。
課題提起 「公益法人制度改革と民間助成活動の活性化」 コーディネーター・山岡義典さん(法政大学現代福祉学部教授)
シンポジスト 鮫島俊一さん(公益財団法人 旭硝子財団:http://www.af-info.or.jp/ 専務理事)
加藤広樹さん(公益財団法人 トヨタ財団:http://www.toyotafound.or.jp/ 常務理事)
秋山孝二(公益財団法人 秋山記念生命科学振興財団:http://www.akiyama-foundation.org/ 理事長)
山岡先生から、民間公益活動の歴史等総括的な流れのご説明があり、次にそれぞれの財団の紹介を兼ねた15分程度のプレゼンでした。私のプレゼンは(2011214e7a78be5b1b1e38397e383ace382bce383b3e69c80e7b582e78988)このような内容です。
当日の模様は、参加者のお一人、日本財団(http://www.nippon-foundation.or.jp/index.html)の荻上健太郎さんが、60近くも驚くほど「つぶやいて」報告して頂いています(http://twitter.com/mash_najo)。まさに「実況中継(?)」ですね!!
民が担う公共の草分け的担い手・山岡先生、日本の民間財団として代表的な旭硝子財団・トヨタ財団の幹部の方とこの機会に何回かお会いして、財団運営の考え方、不断のイノベーション等、実に多くのことを学びました。民間の英知というか、品格の底力みたいなエネルギーを感じて、あらたな勇気が湧いて参りました。
昨日、山岡先生は議員会館での寄付税制の緊急集会でもお話をされていました(http://www.ustream.tv/recorded/12709290)。現在上程中の税制改革法案、是非通過して欲しいですね!!
公益財団法人への移行認定は一つの通過点、先日の秋山財団の理事会・評議員会でも議論されましたが、来年度以降、ホームページをフルに活用して双方向のコミュニケーションを充実させて、さらに飛躍したいと決意を新たに致しました。
貴重な機会を与えて頂きました助成財団センターさまに心から御礼申し上げます、ありがとうございました。