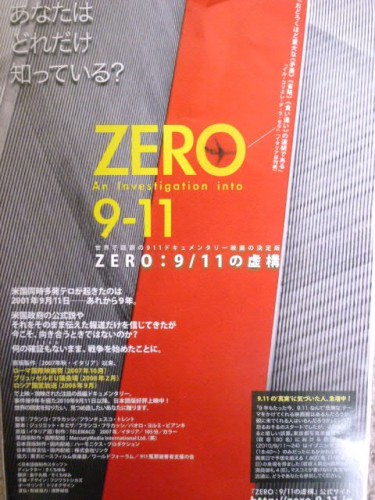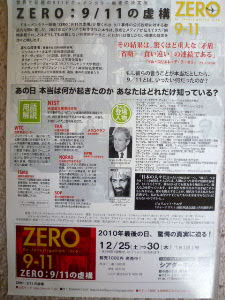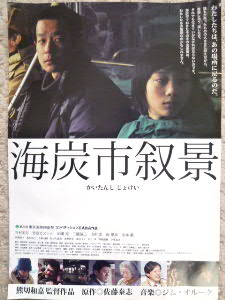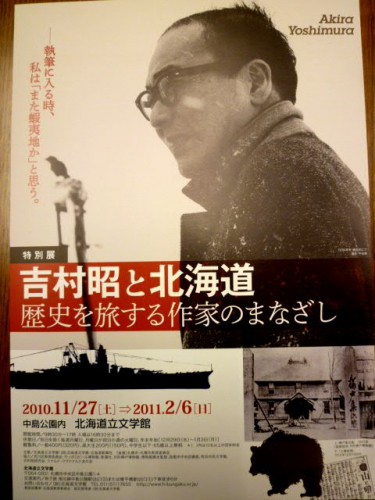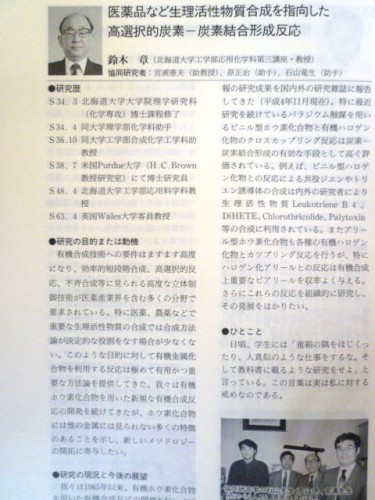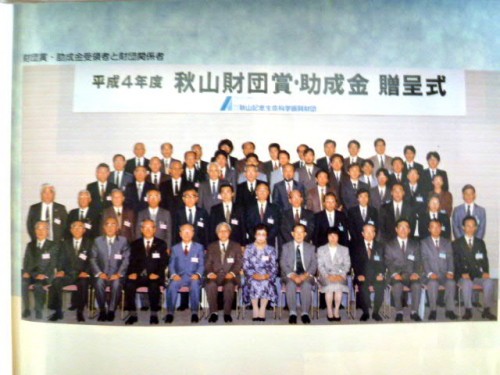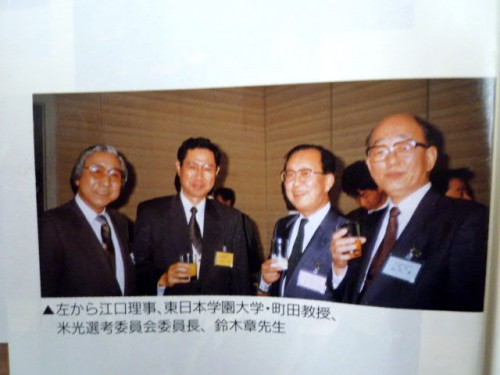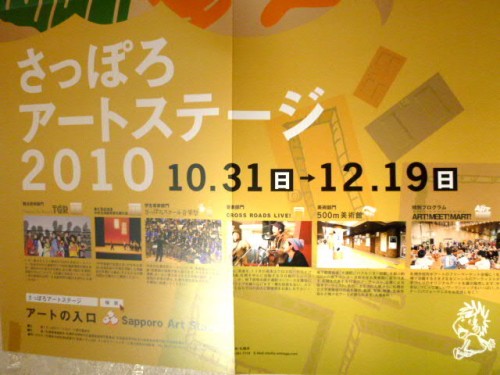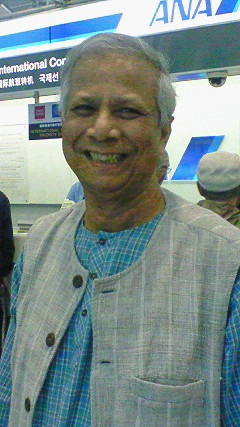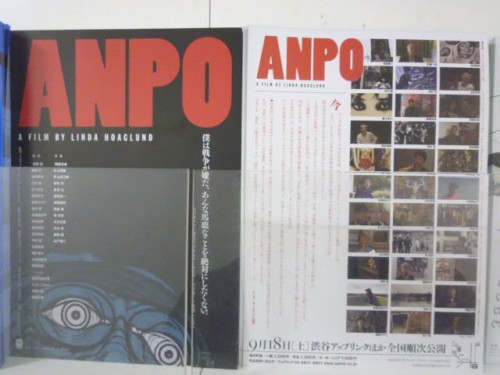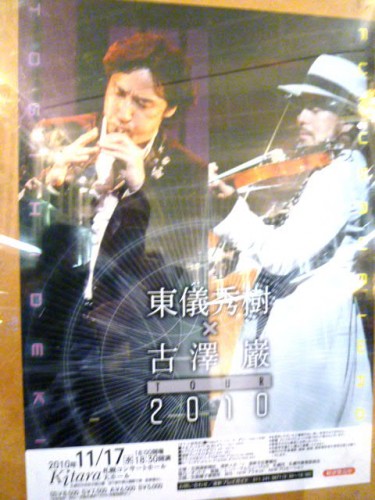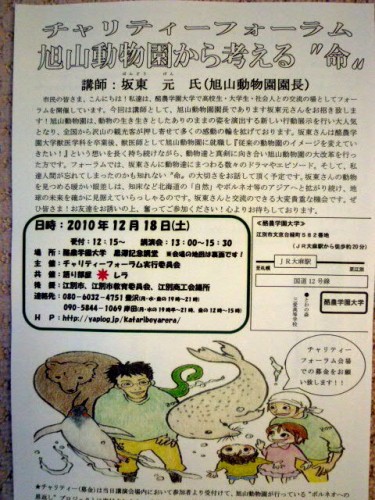今年は、私にとっては情報発信をする機会に恵まれました。この欄は勿論ですが、北海道新聞の1年間の「新聞評」担当、パネルディスカッションのパネラー、札幌劇場祭審査員等です。「新聞評」は、辛口でと担当の方から言われて多少意気込んで取り組みましたが、多くの新聞等も読まなくてはとても辛口での論評は難しく、予想以上の作業でしたね。でも、本当にたくさんの方からの反応も直接頂き、手応えがかなりあったので嬉しかったです。
北海道新聞「新聞評」・担当3回(各1300字)で、以下その抜粋:
<2月上旬掲載>・・・・・・未来は予測するものではなく創り出すものであり、激変期にありながら「従来型」の視座に固執では感動はない。特に「東アジア共同体」構想の国際社会での意味、4つの密約等について、編集には座標軸と原点を示す「覚悟」と「勇気」を期待したい。
<6月上旬掲載>・・・・・・「APEC札幌会合まで1ヶ月」(5日朝刊)、「日本酒外交舞台で存在感」(17日夕刊)に接して、2年前のG8北海道洞爺湖サミットの記憶が蘇った。私は留寿都・国際メディアセンター(IMC)にNGO枠でしばし滞在し、海外からを含めて4000名を越える報道関係者の活きた取材・発信現場を垣間見た。NGOメンバーの記者会見等を含めた真摯で積極的な情報提供活動、市民メディアの的確な課題把握力、日本の映像メディアの浅薄さ、そして質・量ともに贅を尽くしたセンター内の無料飲食メニュー等である。国際会議で大切な地元の姿勢は、上滑りな「おもてなしの心」ではなく、しっかりした議論に裏付けられたメッセージの発信であり、日本のマスメディアに今問われているのは、目の前の状況から課題を認識・抽出する感性と能力なのではないだろうか。
<10月上旬掲載>・・・・・・・・・昨年、足利事件の菅家利和さんが釈放されたのは、元局長が逮捕されるわずか10日前である。多くのメディアは、今年3月に菅家さんの無罪判決が出た時、「捜査の全面可視化」を提起する一方、裁判員制度の導入も踏まえて事件報道のあり方に関して、捜査中心から公判中心へ基本的に転換したはずではなかったのか。本紙には、発表依存の報道から脱却し、以前、道警裏金報道で見せたような、果敢な取材に基づく調査報道の復活を期待したい。
<10月・新聞週間特集(800字)として>~~~~~~~~~
メディアとしての「新聞」の危機は、諸外国の事例で頻繁に語られている。日本では、発行部数の多さ、テレビと内容的に同期している点、広告料の構成比の違い等、特有の環境があり、必ずしも同じ道をたどるとは思えない。ただ、本来の新聞の強みを関係当事者が見失った時、衰退が始まるのだろう。
先月の記事で、私が数社を比較して注目した一行の見出しがある。2010年版防衛白書・閣議報告は「沖縄海兵隊の役割強調」(10日夕刊)、他紙は「防衛白書、薄い民主色」(11日朝刊)と、一歩踏み込んで沖縄普天間問題の迷走との関連を表現していた。また青森県六ケ所村の使用済み核燃料再処理工場問題で、本紙が「再処理工場2年延期」(10日夕刊)とした記事が、他紙では「核燃 展望なき操業延期」(11日朝刊)だった。「安心・安全」への国民の高い関心に応える見出し、記事になっているかどうか、考えていただきたい。
私はこよなく新聞を愛する読者として、期待を込めて望むことがある。一つは、「時代を展望して」、「流れを読んで」と難しいことを言うつもりはないが、少なくともリアルな現場から発せられる「今」を伝えてもらいたい。現場を深く掘る取材によって、「時代の空気」を読者に提供できないものだろうか。もう一つは、「たれ流し」のごとき発表報道ではなく、徹底した取材を基に、主語の明確な検証・調査報道を行ってほしい。発表報道の偏重は、いずれテレビやインターネットへ取って代わられる自滅行為ではないか。
戦前、新聞は「上から目線」の国民教育機能で、権力の監視機能とは大きく性格を異にしており、さらに「報道」が「宣伝」に変わっていった。検証・調査報道の意義は、出来事には時間がたってから分かることがあり、安保・沖縄関連の「密約」でも明らかなように、当時「報道されなかったこと」の意味も、後に検証すると重要性を再認識することができるということである。
市民の視点を貫き、立ち位置を明確にするためにも、記事の検証企画・調査報道にこだわって頂きたい。冷戦後の国際社会、政権交代後の日本社会、今、新しい時代に会社としての「覚悟」が問われているような気がする。
~~~~~~~~~~~~~~~~
パネラーとして:
8月「札幌の芸術都市構想フォーラム」http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=5134
12月「社会起業研究会フォーラム」http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=6770
劇場祭審査員として:
11月札幌劇場祭審査員講評:http://www.s-artstage.com/2010/tgr/2010/12/936/
いずれも多くの皆さま方からご批判、お褒めを頂き、私自身大変励みとなりました。世の中まだまだ先の見えない混とんとした時期が続きますが、やらなければならない事がたくさんあります、来年も一日一日丁寧に生きていきたいものと心に決めています。今年1年、この欄を読んで頂いた方には心から感謝申し上げます。どうか、良いお年をお迎え下さい。