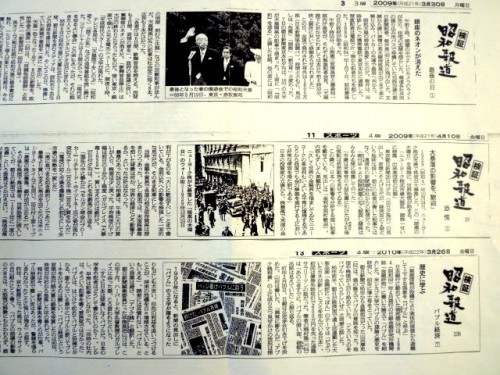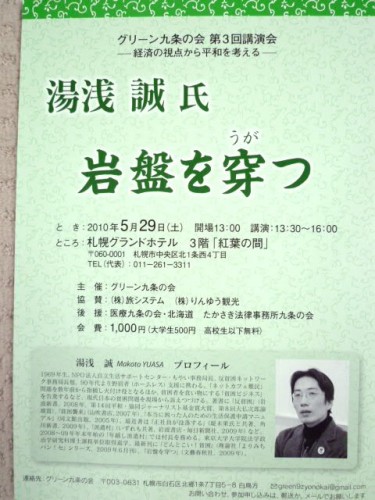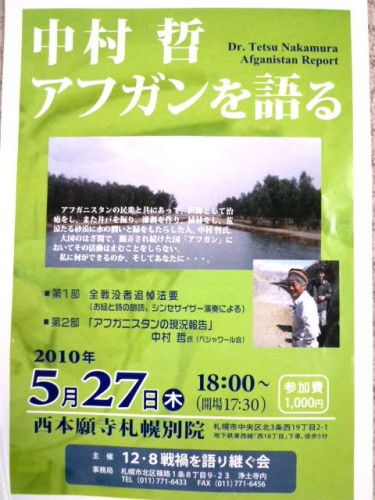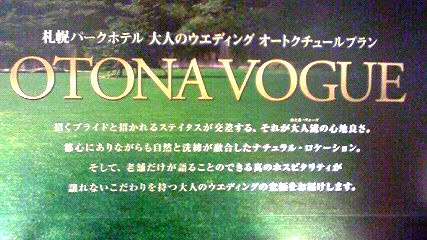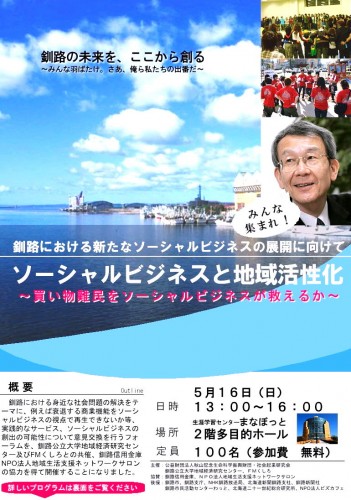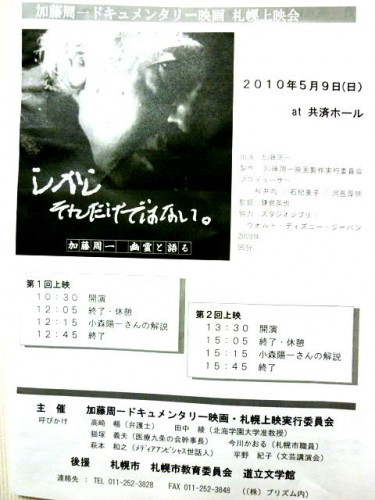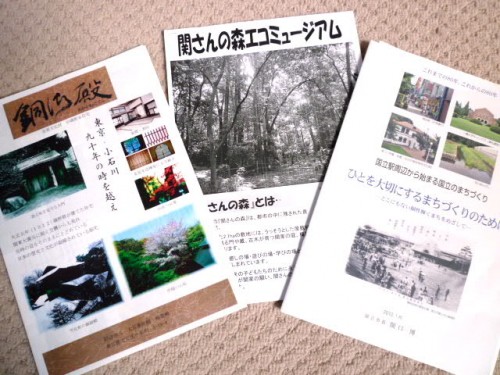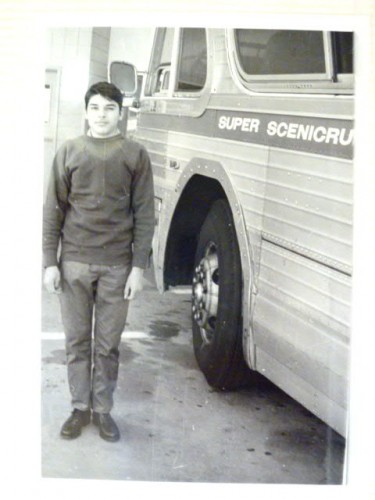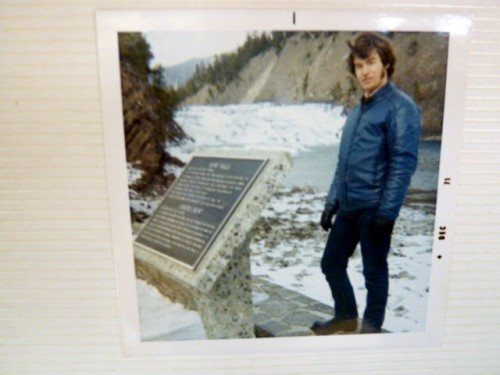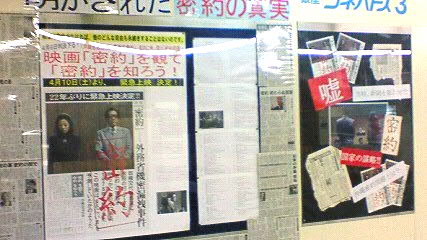先日、朝日新聞シンポジウム「検証・昭和報道」が開催されました。2年間の現場記者20名程を含めた事前検討会議の後、2009年4月から2010年3月まで朝日新聞夕刊に250回連載された「検証・昭和報道」の取り組みに対する総括シンポジウムでした。
取材班から上丸(じょうまる)洋一氏の報告、基調講演として入江昭(ハーバード大学名誉教授)氏、討論(前・後)では船橋洋一(朝日新聞)、入江昭、劉傑(りゅう・けつ:早稲田大学教授)、バラック・クシュナー(ケンブリッジ大学准教授)の各氏がパネラーでした。
<船橋>
*時間が経ってから分かることがある――記事の「検証」機能が必要、現在に鏡をつくること、「調査報道」が無かった
<入江>
*今回の「検証」は、知的に正直な試み
*国内の記事:市民の目をどこまで貫いたか、国家権力の手先となっていなかったか、 国外の記事:欧米大国中心の報道、国際関係の記事:国家権力からの情報・関係性が多い、最近は「交流と共生の昭和史」が書かれるようになってきた
*20世紀の流れ:前半はナショナリズムの台頭、後半は国境を越えた「つながり」(経済・ITネットワーク・移民・避難民・人権・環境・宗教・民族等)
<劉傑>
*歴史の分かれ目をどう理解するか:ロンドン軍縮会議、満州事変
*新聞は「時代の空気を伝える」もの、「流れを読む」、「先を展望する」は別のこと
*戦後は平和を手に入れた:時代の空気は「平和を守る」であり、しばらくは「アメリカの政策に従う」ことであった、80年代に入って、「市民」、「グローバル」等のあらたな視点が生まれてきたのではないか
*「中国報道」をどう行ってきたか:評価の分かれ目、「1945年」は東アジアの多くの国にとって「戦争の終わり」ではない
<クシュナー>
*戦前の日本では、新聞は「第4の権力」ではなく、「政府の一部」だった
*アメリカでは、新聞は200年以上前から「政府を批判する」ことを求められた
*沖縄返還に絡む「密約事件」で、「報道されなかったことの意味」が再認識されるべき、同じ時期のアメリカ・ペンタゴン
ペーパーズ(http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/pentagon/pent1.html)におけるランド研究所ダニエル・エルスバーグは、極秘書類をニューヨークタイムズに掲載、日米を巡る状況の違いは象徴的、「The Most Dangerous Man in America」は、NHK-BS世界のドキュメンタリーで2回にわたり放映された(http://www.nhk.or.jp/wdoc/backnumber/detail/100301.html、http://www.nhk.or.jp/wdoc/backnumber/detail/100302.html
*映画「大統領の陰謀(http://movie.goo.ne.jp/movies/PMVWKPD5664/story.html)」、「フロスト×ニクソン:http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=1064」、このような映画が日本で制作されるだろうか
<その他>
*戦前の新聞は、「上からの目線」で国民の教育機能、国民と国家の間に位置した、調査報道が無かった、「報道」が「宣伝」に変わった、国際秩序をどこまで報道出来たか、昭和の報道は明治以降の「日本」をどう総括するかである
*戦後の報道では、「占領」をどう書けたのか、「東京裁判」で多くの知らない事実が明るみになった
*「冷戦構造」にとらわれ過ぎたのではないか、世界各地では多様な動きが進行していた、特に中国の台頭等
*調査報道は、情報公開法に基づいた「情報公開」活動により実現可能性が高まった
最後に、「ジャーナリズムは検証報道・調査報道ができるかどうかが生命線である」と結ばれました。聴衆は400名を越えていたでしょうか、平均年齢はかなり高かったですね、学生は20名程度だったような気がします。このシンポジウムの詳細は、6月21日朝刊特集面として掲載予定とのことです。