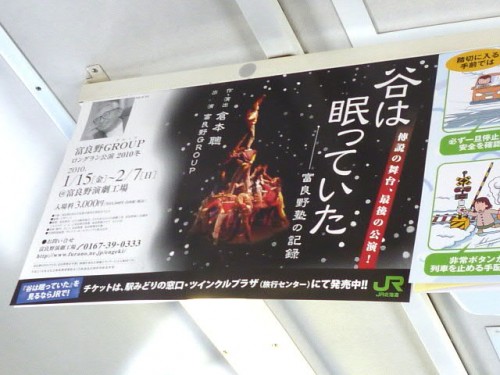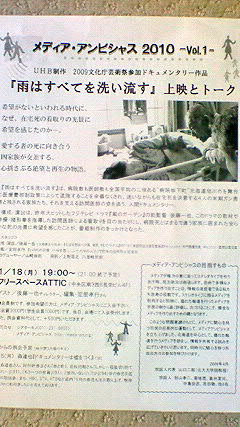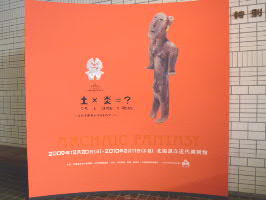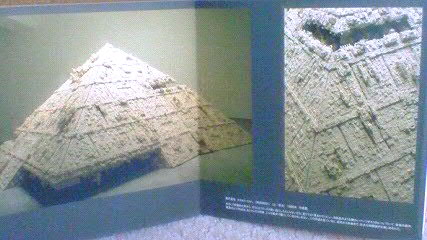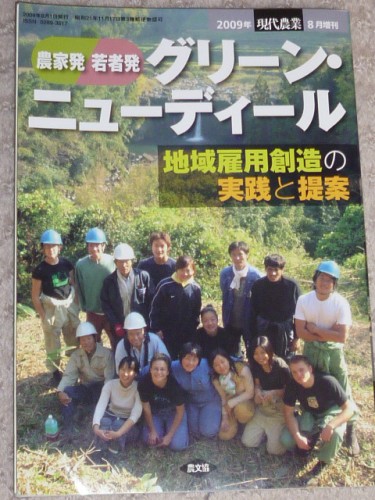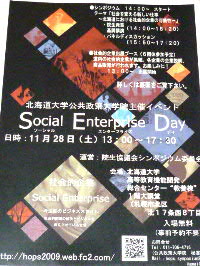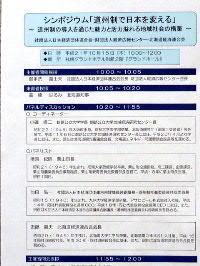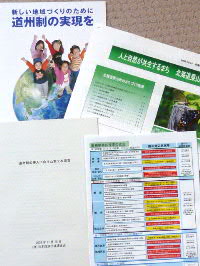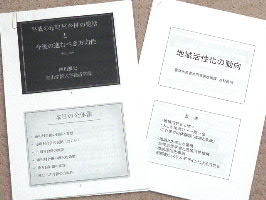昨年5月に、私は「北海道市民環境ネットワーク(きたネット):http://www.kitanet.org/」の理事長に就任しました。この環境系中間支援NPOは、「セブンイレブン緑の基金:http://www.7midori.org/」がメインの支援者で、他に地元企業からも力強く応援して頂いています。今回、「きたネット」が幹事団体となって推進する「『環境分野の中間支援拠点・組織連絡会議』連携型組織づくり事業の確立」が、PANASONIC・NPOサポートファンドの新設されたコンソーシアム助成の第一回目に採択されました。先日、東京・有明の「パナソニックセンター」で贈呈式・交流会・研修会が開催され、出席しました。
パナソニックの企業市民活動http://panasonic.co.jp/cca/の中で、NPOへの助成テーマは「組織基盤強化」です。「子ども分野」と「環境分野」への助成は、松下幸之助氏の「環境革新企業」としての理念の一環でしょう。私たちの今回の取り組みは、1)環境省・北海道環境パートナーシップオフィス:http://www.epohok.jp/(EPO北海道)、2)財団法人北海道環境財団:http://www.heco-spc.or.jp/、3)札幌市環境プラザ:http://www.kankyo.sl-plaza.jp/、と4団体のコンソーシアムで、情報の共有によりユーザーサービスの向上につながる「見える化」の実践が一番の目的です。これから1年間、成果にこだわりながら、少しでも環境分野に携わる北海道民に対して、何か貢献できるものを創り上げたいと思いますね。
会場を去り、「ゆりかもめ」に乗って都心に戻る途中で懐かしい船を見ました。そうです、青函連絡船航路で活躍した「羊蹄丸」と、数多くの越冬隊員を運んだ南極観測船「宗谷」です。「船の科学館http://www.funenokagakukan.or.jp/」の一部として、静かに東京湾に係留されていました。
企業の社会貢献への取り組みは本格的になっていて、それぞれユニークな目的を持って「新しい公共」の一翼を間違いなく担っていくと思われます。これからも企業セクターと本来の意味の「第三セクター(非営利セクター)」とのコラボレイトに期待がかかります。