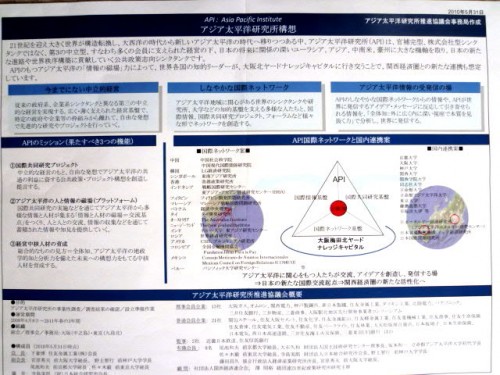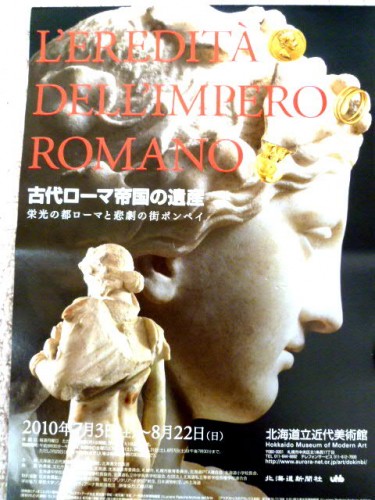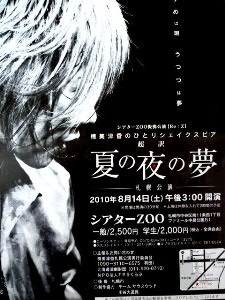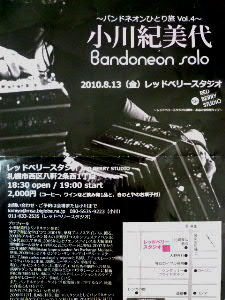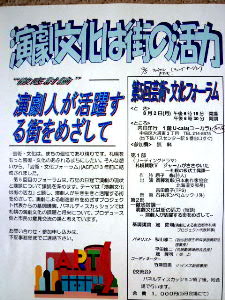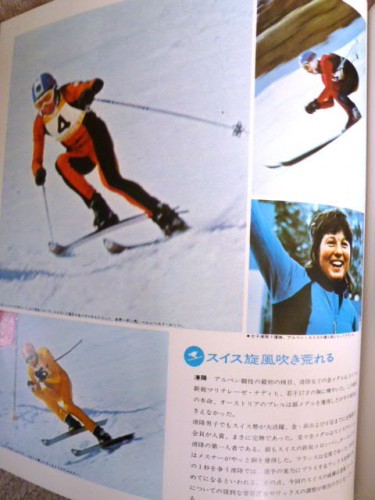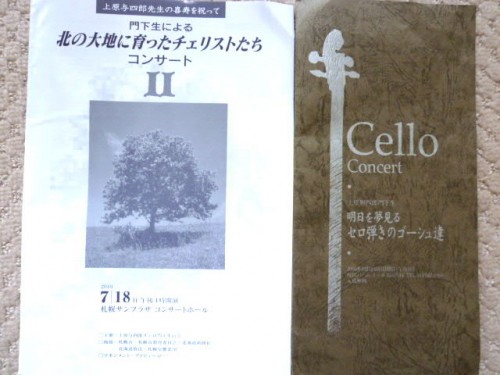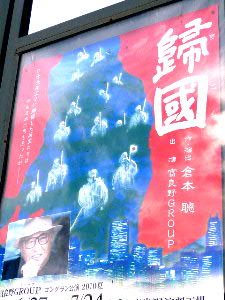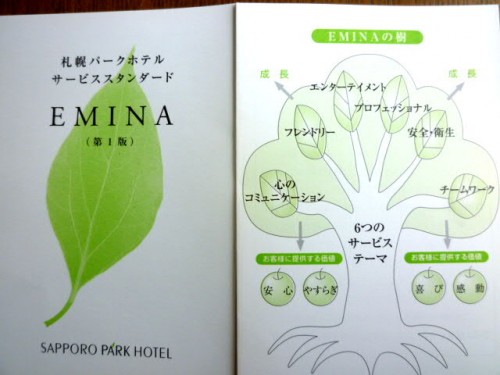今年のサッカーW杯南アフリカ大会、海外でW杯初勝利、自国開催以外で初のベスト16進出の輝かしい成績に日本代表を導いた岡田武史監督が、幾つかの新聞に率直な気持を吐露しています。昨年の8月にこの欄で、私は高校野球の香田誉士史監督に感謝の気持を書きました(http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=1904)。素晴らしい成績の裏には、必ずそのチームの監督の突き抜けた努力と哲学がありますね。今年の春・夏連覇の高校野球、沖縄県代表の興南高校(http://senior.konan-h.ed.jp/)・我喜屋優監督も全く同様です。
新聞によれば、岡田監督は鳩山首相から菅首相に代わったことを知らないほど、W杯へのチームづくりに集中していたようです。また、一時、大会終了後は農業に従事したいとの報道も流れましたが、あれは外国メディアに「晴耕雨読:せいこううどく」を英語で説明した所、「晴れた日には土を耕す」の部分だけが報道されたと自分の英語力の不足も語っていました、聞いてみないと分からない、面白い話ですね。
「自分の理想としては『美しい』だけではだめ。確かに戦術的にはバルセロナ(バルサ:http://www.fcbarcelona.jp/)のようなサッカーが好きだけど、必死にプレーする選手を見て、なんでこんなに必死になってボールを追っているのかという感動がプラスされないとダメだと思う。理想のサッカーを問われれば、戦術的なことよりも、まず感動だと考える」
パラグアイ戦の直後のコメント、「もう一試合やらせてやりたかった」。そして後日、「選手たちは代表として無心になっていた。しかし、何だかんだ言いながら、ベスト16になって周囲からすごいと言われて、どこか満足している自分がいたのだと思う。それを何とか追い払おうと選手にも強いことを言ったりしたが、あそこで勝てず、最後の自分に執着心が足りなかった。経験が無いから最後のハングリー精神がなかったと、負けた瞬間に直感的に感じた」と振り返っていました。
我喜屋優監督は、春の選抜大会で優勝した翌日から、「優勝チームはすでに終わり、またゼロから夏に向かって新しいチームをつくろう!」と生徒たちに厳しく語り、基礎練習からやり直したそうです。夏の優勝直後のインタビューでは、「夢がかないました、沖縄県民の!」。いずれも修行僧のような自己に対する厳しい姿勢、そして哲学、まさに勝つべくして勝った、そんな気がしますね。
岡田監督、我喜屋監督とは比べものにはなりませんが、30数年前の私の監督経験(http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?p=27)でも、似たようなことを感じました。忘れもしません、都大会準々決勝でした。私が教員だった中学校の女子チームは、江戸川区新人戦で優勝、夏の地区大会でも準優勝、そして区代表として全都560校の代表チームで戦う都大会に出場して次々と勝ち上がり、準々決勝に進みました。1セットを取り、2セット目も7-0と圧倒的にリード、監督の私は次の準決勝のこと、更に全国大会への出場を一瞬考えたのです。そんな集中力を欠いた雰囲気が瞬間選手たちに伝わったのか、あれよあれよという間に追い上げられて、追いつかれて、逆転され、セットを失い、変わった流れを元に戻すことが出来ずに、結局次のセットも失って敗戦となりました。
試合後、私は無言で選手と一緒に遠い学校に戻って、反省会で子供たちに謝りました。「君達にはまだまだ試合をさせてやりたかった。先生の油断と志の低さで申し訳ないことをした」と。心のどこかで都大会ベスト8で満足していた自分が居たのだと思います。本当にあの時の子供たちは、控えの選手も含めて1年間363日練習に明け暮れて、良く努力しました。自分にもう少し経験があれば・・・・、人生であまり後悔というのはないのですが、今でも悔いの残る試合でした。「自分自身がしっかり目指していなかった」、そんな自らの甘さを誰よりも自分が感じていましたね。
その後経営者として全責任を負う立場に就いた時、私はこの監督経験から学んだことを肝に銘じていました。強い信念を持ち、しっかり構想して、集中力を持続し諦めずにやり抜くこと、それが組織責任者のあるべき姿だと。
この数カ月、素晴らしいチームを育て率いた監督から、沢山のメッセージを受け取りました。岡田武史監督、我喜屋優監督、本当にお疲れさまでした。